木炭(いわてお国自慢)

このページでは、岩手県が日本一、日本初あるいは唯一無二であるなど、全国に誇るべき岩手のお国自慢をご紹介します。
今回は「木炭」!
広大な森林をもつ岩手県には、木炭の原料となるナラが豊富にあります。県北部の市町村が中心となって生産している木炭は、全国生産量注の約2割を占め、日本第2位(令和5年)のシェアを誇っています。
- 第1位 高知県 :全国シェア23.9%(1,512t)
- 第2位 岩手県 :全国シェア22.2%(1,399t)
- 第3位 和歌山県:全国シェア14.8%(935t)
岩手の木炭生産の歴史は古く、約900年前の平安時代からと言われています。平泉遺跡群発掘調査では、12世紀前半頃から陶器を焼く際の熱源として木炭が使われていたことが分かっています。
「岩手大量窯」を使用し、窯内を均一の温度に保ち時間をかけて丁寧に製炭することで、樹皮をあまり剥がすことなく炭化させることができます。このことにより、「岩手木炭」の大きな特徴でもある高い着火性能が生まれます。
「岩手木炭」の特徴は、火付き、火持ちに優れ、バーベキューに最適です。また、不純物が非常に少なく、煙や臭いがほとんど出ないため、いやな匂いが食材にうつらないのも魅力です。
さらに、燃焼温度が高く、遠近赤外線で食材全体をすばやく加熱できます。これによりうまみ成分や肉汁を逃がさず、外側はカリッと内側はふっくらジューシーに仕上がります。
是非アウトドアや飲食店などで、岩手木炭の良さを体感してください。
注:林野庁「特用林産基礎資料」木炭(黒炭+白炭)生産量
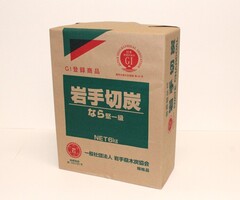


岩手県では、平成2年度から、環境に優しい木炭の利用啓発と岩手木炭の品質の良さをPRするとともに、木炭産業の健全な発展に資することを目的に「岩手県木炭品評会」が開催されています(主催:一般社団法人岩手県木炭協会)。
岩手県木炭品評会は、国内唯一の農林水産祭参加行事であり、令和6年度大会では、出品点数100 点以上の岩手木炭の中から、厳正な審査の結果、洋野町の新田徳男氏が黒炭切炭の部で農林水産大臣賞、久慈市の上平明男氏が黒炭長炭の部で林野庁長官賞、茶用木炭の部で岩手県知事賞を受賞しました。


県では今後も、生産者の皆さんとともに岩手木炭の生産振興に取り組んでいきます。
豆知識
【もくたん(木炭)】
- 製炭方法(焼く温度)の違いによって黒炭と白炭に区分される。[黒炭:400~700度、白炭:約1300度]
- 「岩手木炭」が平成30年8月6日に地理的表示(GI)の登録を受けた。
(注)地理的表示(GI)とは、地域の商品ブランドに国がお墨付き(知的財産として保護するなど)を与えるもの。県内では「前沢牛」「岩手野田村荒海ホタテ」に続き3例目。木炭の登録は全国で唯一。 - 岩手県の製炭者数(木炭の生産者数)は全国2位。
(注)岩手県製炭技士(チャコールマイスター)養成研修などで若手生産者などの育成を支援している。 - 県沿岸部の住田(すみた)町には、木炭をモデルにした「すみっこ」というゆるキャラがいる。

関連情報
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 林業振興課 振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5776 ファクス番号:019-629-5779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
政策企画部 広聴広報課 広聴広報担当(広報)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5283 ファクス番号:019-651-4865
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

