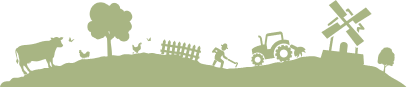しそ巻き寿司
岩手県食の匠:飛田奈都子(令和元年度認定)

大槌町の山間部において、赤紫蘇は身近な食材として重宝されていました。とりわけ、昔は海苔が貴重品であったため、巻き寿司を作る際は、赤紫蘇を塩蔵し、海苔の代わりに使っていました。現在では、健康に配慮し酢で漬ける作り方に変わっています。
また、しそ巻き寿司は冠婚葬祭のごちそうで、祝い事では赤色の具材を必ず使用していました。
材料(3人分(太巻き1本分))
-
〔赤紫蘇の酢漬け〕
赤紫蘇
砂糖(A)
穀物酢(A) -
40枚
20g
大さじ4
-
〔寿司飯〕
うるち米
もち米
水
砂糖(B)
塩(B)
穀物酢(B) -
300g
30g
350ml
25g
2g
大さじ4
-
〔厚焼き玉子〕
卵
砂糖
塩
サラダ油
-
4個
6g
1g
適量
-
〔しいたけの煮物〕
干ししいたけ
しょうゆ
みりん
砂糖
水
-
10枚
大さじ2
大さじ1
5g
300ml
-
〔きゅうり塩漬け〕
きゅうり
塩
-
1本
3g
-
〔巻き寿司〕
赤紫蘇(酢漬け)
寿司飯
厚焼き玉子
しいたけの煮物
きゅうりの塩漬け
くるみ
梅干し(大) -
40枚
600g
2本(1本あたり幅2cm×厚さ1cm×長さ15cm)
70g
縦1/4本×2本
30g
2個程度
作り方
〔赤紫蘇の酢漬け〕
1 赤紫蘇を洗って水気をしっかり切る。
2 「1」の赤紫蘇を3枚ずつ取り、よく混ぜ合わせた調味液Aにまんべんなく浸し、容器に重ねて入れる。余った調味液Aは、容器に入れた赤紫蘇にかける。
3 「2」の赤紫蘇に1kgほどの重石をのせ、常温で4時間程度置いたら、軽く水気を切って密閉容器に入れ、冷蔵庫に入れる。
〔寿司飯〕
1 うるち米ともち米を合わせて研ぎ、分量の水を加えて30分吸水させ炊飯する。
2 炊きあがった「1」のご飯をすし桶等に入れ手早くほぐし、よく混ぜ合わせた調味液Bを回し入れながら、しゃもじで切るようにしてなじませる。
〔厚焼き玉子〕
1 分量の卵をボウルに割り入れ溶いたら、砂糖、塩を加え混ぜ合わせる。
2 玉子焼き器(縦19cm×横13cm)にサラダ油を薄くひき、中火で熱したところに「1」の卵液を流し入れる。
3 焦げないように外側から箸で全体をつつき、卵液の表面が固まってきたらフライ返しでひっくり返す。
4 3秒ほど焼いたら火を止め、余熱で火を通す。
5 「4」をまな板の上に置き、冷めてきたら、縦長に幅2cm程度のものが6本くらいできるように切る。
〔しいたけの煮物〕
1 干ししいたけを300mlの水に浸けて戻しておく。戻した後は、出汁に利用するため、戻し汁は残しておく。
2 軸を切って厚めにスライスする。
3 鍋にしいたけと戻し汁を入れて中火に5分程かける。沸騰し始めたら、調味料を加え、汁気が少なくなり、味が浸みこむまで煮詰める。
〔きゅうりの塩漬け〕
1 洗ったきゅうりに塩をふりかけ、まな板の上で転がし、しばらく置く。
2 水でさっと流してから両端を切り落とし、縦方向に4等分に切る。
〔梅干し〕
1 リンゴの皮をむく要領で、梅干しを回しながら果肉を1本の長さに切る。
〔巻き方〕
1 赤紫蘇(酢漬け)は巻きすの下方から並べる。1段目は広げた巻きすの左下に赤紫蘇(酢漬け)の葉を裏返しにして縦に置き、右方向に7枚程度並べる。その時、葉の右側3分の1に次の葉を重ね、ずらして置いていく。
2 「1」の左下に置いた葉の中央に軸がくるように2段目の葉を置き、「1」と同じ要領で右方向に7枚程度並べる。同じ要領で隙間ができないよう巻きす全体が隠れるまで葉を並べる(5段程度)。
3 「2」の下側1cm、上側5cmほど空けて、寿司飯を1cm程度の厚さに広げる。
4 「3」で広げた寿司飯に、菜箸を使い下から2cm間隔で溝を5本つける。
5 「4」でつけた溝に、手前から厚焼き卵、きゅうりの塩漬け、梅干し、しいたけの煮物、くるみの順に敷き詰める。
6 手前の巻きすの下の両端を持ち、厚焼き卵と寿司飯を空いた指で押さえながら寿司飯が崩れないように少しずつ巻き込む。全体の4分の1くらいまで巻いたら、寿司飯の端まで一気に巻いていく。
7 巻きすを外した寿司をラップで包んでから左右をねじる。左右をつまみ、前後に転がしてから2回ほど軽く叩き、型崩れを防ぐ。
8 「7」を少なくとも30分以上置いてから、両端を切り落とし、3cm程度の幅に切り、皿に盛る。
料理のポイント
1 旬の赤紫蘇の色鮮やかさが失われないように、長時間の漬け過ぎに気を付ける。
2 赤紫蘇(酢漬け)は、時間の経過に伴い色あせるが、冷蔵保存で1年ほど保つ。
3 巻きすで巻くときは、ゆるすぎず、かつ、ぎゅっと固く締め付けすぎないこと。滑らかに巻きあげ、形を整える程度にすると、寿司飯の粒感が引き立たち美味しくなる。
4 穀物酢の代わりに五倍酢を使うと、赤紫蘇の酢漬けが色鮮やかになり、より酸味の効いた味に仕上がる。
5 仏事では、かんぴょうやしいたけ、ごまなどを主に用い、赤色の具材は使用しないか使用しても量を控える。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
大船渡農業改良普及センター
〒022-0004 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-27-9918 ファクス番号:0192-27-9936
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。