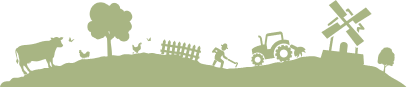鮭の紅葉漬け
岩手県食の匠:東谷幸子(平成21年度認定)

昔から豊富に獲れる鮭を活用して、秋から冬にかけて作られてきた郷土料理であり、主に正月料理として振舞われていました。
鮭の身といくらが入っているため、見た目が紅色で鮮やかなことから「紅葉漬け」と呼ばれています。
材料(5人分)
-
生鮭(銀毛)
いくら(はらこ)
振り塩
塩蔵昆布 -
200g
50g
20g
5g
-
〔漬け汁〕
しょうゆ
みりん
酒
塩 -
200cc
200cc
50cc
少々
下準備
1 新鮮な鮭を三枚に下ろす。
2 いくらを金網などを使い粒をほぐした後ザルに移し、人肌程度の温度のお湯をボウルに注ぎ、その中にいくらの入ったザルを入れる。いくらの表面が白くなったら、お湯を捨てる。
3 「2」を3%の塩水を取り替えながら10分程度おけの中で洗い、その後ザルに上げておく(冷蔵庫で保存)。
4 「1」を冷凍する。(-20℃以下24時間以上:寄生虫対策)
作り方
1 塩蔵昆布は水で洗い、塩抜きして細切りにする。
2 「1」と漬け汁の材料を鍋に入れ、さっと煮立てて冷ましておく。
3 冷凍した鮭を解凍し、皮と骨を除く。その際に、身の中の小骨を丁寧に毛抜き等で取り除く。その後一口大の大きさに削ぎ切りにする。
4 「3」の切り身をまな板の上に広げ、表面を軽く覆うくらいの塩(20g程度)を振りかけ、20分置く。
5 「4」を冷水で塩を落としながらよく洗い、水気を十分に切る。
6 容器に鮭といくらを入れ、「2」をひたひたに隠れるくらい注いで一晩冷蔵庫に入れ、漬けておく。
7 具材を漬け汁から上げてから食べる。お好みでとうがらしを振りかけても良い。
料理ポイント
1 鮭は「銀毛」を使うと脂がのって、発色もよい。
2 いくらにお湯を注ぐ際、温度が高すぎると皮が固くなるため注意する。
3 いくらは十分に塩水でかき混ぜて洗うことで皮が硬くなるのを抑え、味が染み込みやすくなる。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
大船渡農業改良普及センター
〒022-0004 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-27-9918 ファクス番号:0192-27-9936
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。