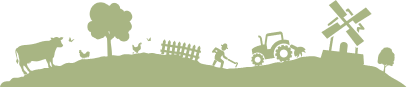《ルポ・花北》いわてきたかみ牛の消費拡大に向けて 〜JA いわて花巻北上地域肉牛部会〜
ルポルタージュ産地・人を訪ねて 2010年1月号
いわてきたかみ牛の消費拡大に向けて
JA いわて花巻北上地域肉牛部会
北上市は、岩手県の中央部に位置し、平野部が多く水稲を中心に大豆・麦・園芸・畜産等の作目を組み合わせた複合経営もみられます。肉用牛では、肥育牛の占める割合が高くなっています。

「いわてきたかみ牛」の銘柄確立
平成5年に東京食肉市場で開催された全国肉用牛枝肉共励会において、部会から出品された牛が和牛去勢の部で最優秀賞を受賞したことがきっかけとなり、部会員の間で互いに技術研鑽さんを図って肉質改善に努め、きたかみ牛を産地銘柄として確立させようとする機運が高まりました。その結果、全国や県で開催される枝肉共励会・研究会等で上位入賞をするようになり、今日の「いわてきたかみ牛」銘柄確立の礎となりました。
現在使用している「きたかみ牛」の押印は、平成7年8月に東京食肉市場へ出荷した枝肉から始め、平成16年には「いわてきたかみ牛」として商標登録を取得しています。これらが部会員を発奮させる原動力となり、上物率(4等級以上)は、年々向上して、平成20年では上物率73.0%(同年の黒毛和種去勢県平均51.4%)となっています。
また、これらの取り組みが認められ、平成21年度のいわて農林水産振興協議会長(会長・岩手県知事)表彰の「個性ある産地づくり賞」を受賞しました。
ニーズにあった枝肉生産の取り組み
売れる枝肉を作るためには、市場関係者や購買者側のニーズを把握することも重要と考えています。
部会では、年数回行われる北上地域の枝肉共励会・研究会の機会を利用して、需要の高い枝肉や飼養管理上の注意点等について、市場関係者や購買者と直に意見交換を行っています。
また、毎年購買者を北上市に招き、多くの部会員が情報を得ると同時に、購買者との間に良好な信頼関係を構築するよう努めています。



危機を逆手に「きたかみ牛」をPR
飼料高騰や、平成20年秋以降の経済不況の影響から牛肉消費の減退など、肉用牛農家を取り巻く環境は厳しいものがあります。その中で、自分たちの生産する牛肉の安全・安心を直接消費者にPRすることで、牛肉の消費拡大を図ろうと、様々な取り組みが行われています。
- 首都圏や市内の百貨店・量販店における消費者への牛肉試食販売
- 牛肉料理レシピの提供
- 毎年開催される「きたかみ牛まつり」での牛肉試食の実施、生産者情報等の提供
- 市内ホテルにおいて消費者が牛肉料理の試食をする「きたかみ牛食フェスタ」を開催(4回)
- 市内ホテルにおいて期間限定でランチメニュー化(平成21年3月)
これらの取り組みの中心となっているのは、肉牛部会女性部のメンバーです。



「ビーフレディースきたかみ」の活躍
BSE発生による危機を乗りきるため、平成13年に農協肉牛部会女性部のメンバーが中心となって結成されたのが「ビーフレディースきたかみ」です。
結成直後、首都圏の百貨店まで出向いて「きたかみ牛」のPR隊を務め、以降も神奈川県や市内の量販店等で開催している牛肉試食販売を担当し、消費者に飼養管理状況や牛肉料理レシピの提供等、牛肉の消費拡大に向けた情報発信に努めています。
また、「きたかみ牛まつり」では牛丼や牛肉煮込み等を販売し、毎年好評を得ています。
そろいのカウボーイハットで東京市場や各種イベントに登場する様子は、颯爽としており必見です。



若手後継者グループの結成
北上市では、20〜30代前半の若い後継者が就農し、仲間同士で技術を磨きながら熱心に農業に取り組んでいます。しかし、北上地域の肉牛生産を振興するためには、北上で牛肉生産に携わる全ての若者が力をあわせる必要があるとの考えから、平成21年7月に「KITAKAMI 牛研究会」が設立されました。
メンバーは農協肉牛部会員の後継者に加えて、北上にもう一つある肉牛出荷組合の後継者、農業法人の雇用者も参加しています。
また、NOSAI 獣医師がアドバイザー会員として参加し、普及センターとともに活動への助言を行っています。
主な活動内容は、(日曜)生産技術向上のための勉強会、(月曜)消費者への生産情報発信です。NOSAI 獣医師が参加しているメリットを活かし、血液検査の実施等、飼養管理改善に向けた取り組みを行っています。消費者への情報発信としても、きたかみ牛のPRビデオを作成し、平成21年の「きたかみ牛まつり」で上映する等、活発な活動が行われています。
メンバーの中には、集落組織のオペレーターとして活躍している会員もおり、今後の地域農業の担い手としても期待されています。



顔の見える産地を目指して
当初は、県内の有力産地に追いつけ追い越せを目標に始まった銘柄確立への道ですが、数々の危機を契機に、消費者に産地情報を提供することの重要性を部会員全員が認識するようになりました。
今後も「いわてきたかみ牛」の情報発信に努め、消費者に「いわてきたかみ牛なら大丈夫」との安心感を与えられるような産地となることを目指しています。
(中央農業改良普及センター多田浩美)
このページに関するお問い合わせ
中部農業改良普及センター
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4464 ファクス番号:0197-68-4474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。