北東北3県関係者が集い情報交換 ~ 日本短角種の現状と課題について
平成26年1月28日、盛岡市内のホテルで「平成25年度日本短角種振興協議会研修会」が開催されました。この協議会は、北東北3県が連携して日本短角種の生産振興を図ることを目的として昭和61年に設立され、構成員は生産者団体と主産地市町村等の36団体・機関となっています(会長:岩泉町長)。
75名が出席した研修会では、筆者から「岩手県における日本短角種の現状」と題して、これまでの改良成果と今後の課題について説明させていただきました。本県でも繁殖資源が縮小する中で、近交系数が上昇する傾向(課題)にあり、これを回避するための計画的な種雄牛配置や人工授精の活用について、お話ししました。
続いて、帯広畜産大学の口田圭吾教授による「日本短角種の新たな肉質評価法」と題した基調講演が行われました。現在実施されている牛肉の格付は、サシ(脂肪交雑)を重視した黒毛和種には向いているものの、赤身が売りの日本短角種にはなじまないことが、これまでも言われ続けてきました。この講演では、「きめ・しまり」をより細分化して評価することや、枝肉の外観と食味が関連する可能性など、興味深い内容のお話を聞くことができました。
研修会終了後、アンケートを行ったところ日本短角種に関する研究として最も期待する分野は「食味」で、次いで「発育」となりました。日本短角種の地域における位置づけとしては、最も多かったのは「継承すべき財産」で、次いで「重要な特産品」となりました。改めて、日本短角種に対する関係者の意向・ニーズを知る有意義な研修会でした。
-
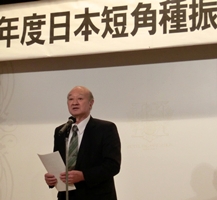
研修会冒頭であいさつする岩泉町長
-

熱心に聴講する参加者
-
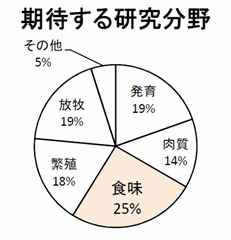
アンケート結果(1)
-
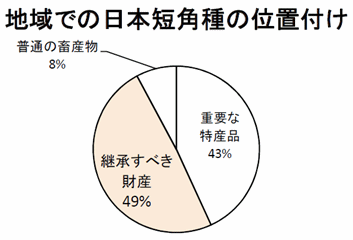
アンケート結果(2)
(畜産研究所家畜育種研究室 主任専門研究員 鈴木 強史)
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 畜産研究所 家畜育種研究室
〒020-0605 岩手県滝沢市砂込737-1
電話番号:019-688-4328 ファクス番号:019-688-4327
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
