日本短角種改良の「最後の砦」は責任重大! ~ 平成25年度日本短角種現場後代検定を開始
日本短角種は、主に、北東北3県(岩手県・青森県・秋田県)と北海道で飼養されており、その中で、本県は最大の産地となっています。日本短角種の強みは、「夏山冬里・自然交配」注)による省力的な子牛生産体系にあります。この体系を維持するためには、自然交配用の種雄牛を作り続けなければなりません。また、種雄牛は、次の世代の子牛を生産するためのものですから、改良を前進させる上で望ましい能力が備わっているかどうか、明らかであることが求められます。
日本短角種種雄牛の能力調査では、第一段階として、一定の基準で選抜された種雄牛候補牛の発育・体型等を調べて、比較を行います。これが「直接検定」と言われるものです。続く第二段階では、まず、直接検定成績上位候補牛の子牛を生産し、この子牛20頭を一般の農家で肥育してもらい、生産される牛肉の量や質の状態を調べます。これが「現場後代検定」と言われるものです。種雄牛の価値は、その後代(種雄牛を父に持つ子牛)がいかに高い能力を発揮するかにあるので、この2段階の検定が不可欠ということができます。
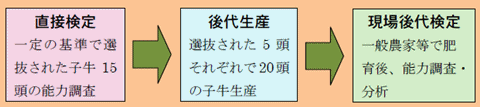
かつて、同様の方法を採っていた青森・秋田両県では、繁殖雌牛頭数が検定用の子牛を確保できないまでに減少したため、このような体系的種雄牛造成から撤退し、現在実施しているのは本県のみとなってしまいました。
平成25年度も直接検定を終え、成績上位だった5頭について、11月から現場後代検定を開始しました。検定終了は、平成28年2月の見込みで、直接検定の開始からほぼ5年後となります。長い道のりですが、唯一の種雄牛造成県として、日本短角種の改良に果たす責任の重大性を意識しながら、検定に取り組んでいきたいと思います。
注)夏山冬里・自然交配
日本短角種の子牛生産の一般的な方法。春(5月中旬)に、生まれた子牛と母牛を公共牧場に放牧し、一頭の種雄牛と混牧。母牛は、自然交配で再び妊娠(受胎率9割超)し、秋(10月下旬)には成長した子牛とともに里の牛舎に。放牧期間中、飼い主は、畑作などに専念したり、農業以外の仕事に従事して収入を得ることが可能。
-

後代検定牛の体重測定
-

後代検定牛各部の計測
(畜産研究所家畜育種研究室 主任専門研究員 鈴木 強史)
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 畜産研究所 家畜育種研究室
〒020-0605 岩手県滝沢市砂込737-1
電話番号:019-688-4328 ファクス番号:019-688-4327
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
