計画的作付プランで多収&低コスト ~ 非主食用稲の湛水直播での生育予測技術
岩手県内では、転作作物として非主食用稲(飼料用米や稲ホールクロップサイレージ等)の作付けが拡大しており、その中で、省力技術である直播栽培で非主食用稲を生産する農家が増えています。岩手県農業研究センターでは、粗玄米収量800kg/10アール、生産コスト30%削減をめざして、直播栽培技術の開発に取り組んでいます(農林水産省「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」)。
直播栽培は、移植栽培に比べ生育が遅れることから、直播栽培で収量を増やすためには、品種の選択や作付計画が重要です。その地域の気象条件で、「どの品種を、いつ播種すれば、いつ頃出穂するか」が分かれば、予め品種の選択や作付計画の検討ができ、安心して直播栽培に取り組めるようになります。
そのため、プロジェクト推進室では非主食用品種を湛水直播で栽培した場合の生育予測技術の開発に取り組んでいます。平成23年度は、センター内(北上市)で栽培した場合の、非主食用品種「つぶみのり」と「つぶゆたか」について、出穂期を±3日程度の誤差で予測することが可能でした。平成24年度は、現地試験で検証を行う予定としています。
この他にも、プロジェクト推進室では、非主食用稲の多収・低コスト生産のために、播種機の開発や新たな播種方法についても試験を行っています。
-

播種時期をずらして栽培した場合の穂の様子(撮影日:平成23年8月1日)
播種時期は、左から4月28日、5月10日、5月23日、5月31日
播種時期を変えるだけで穂の発達がこんなに違います -
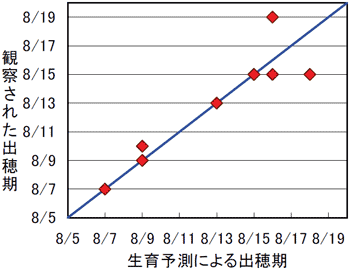
生育予測と観察された出穂期の比較
±3日程度の誤差で出穂期を予測することができます
(プロジェクト推進室 主任専門研究員 臼井 智彦)
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 生産基盤研究部 生産システム研究室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4413 ファクス番号:0197-71-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
