小さな芽が残した大きな宿題 ~ 機械除草を中心とした大豆無除草剤栽培技術(2)
プロジェクト推進室(特栽・有機)では、大豆の減農薬栽培技術の開発に取り組んでいます。前回は、機械除草の方法などを紹介しましたが、今回はその結果についてお知らせします。
大豆の出芽直前から7月上旬まで、合計4回の機械除草を行い、その後は通常の栽培と同様に、中耕・培土を行いました。機械除草を行った直後は、一見、雑草がほとんど無くなったように見えるのですが、大豆の株と株の間に小さな雑草が多く残ってしまい、その後の培土等の作業によっても、雑草の生育を抑えることが出来ませんでした。そのため、除草剤を使用した慣行栽培に比べ、収量が約20%減少しました。
以上のように、これまでの試験結果から、現場で利用するために解決すべき課題が多く見つかりました。平成23年度からは、「水田転作における大豆の除草機を中心とした除草技術の確立」という新しい研究課題で、水田転作での大豆の雑草対策に取り組んでいく予定としています。
-

作業中の固定式タイン型除草機(平成22年7月1日)
作業直後は、一見すると非常にうまく除草出来ているように見えますが…… -

機械除草直後の株間の雑草(同日)
大豆の株元には多くの小さい雑草が残っています -

その後の雑草の様子(平成22年7月7日)
条間には雑草はほとんど見えませんが、株間に残った雑草が大きく生育しつつあります -
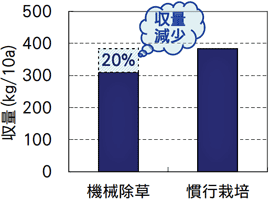
大豆の収量の比較
除草剤を使用した慣行栽培に比べ、約20%の減収となりました
(プロジェクト推進室(特栽・有機) 主任専門研究員 臼井 智彦)
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 生産基盤研究部 水田利用研究室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4412 ファクス番号:0197-71-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
